あけましておめでとうございます。
ウェブテクノロジ代表の小高です。
OPTPiX Labs Blog内検索
カテゴリー
アーカイブ
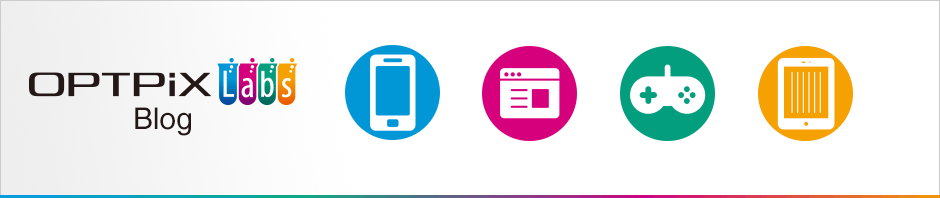
『ゲーム制作の民主化』という壮大なテーマでもって業界ならず昔で言う『日曜プログラマ層』をダイナミックにとりこむことに大成功したゲームエンジン、Unity。その”Unity Technology”社が同エンジンのユーザー向けに、国内外の事例紹介と耳寄りな情報を大紹介するイベントが開催されます。その名も「Unity Asia Bootcamp Tour」! このイベントに、弊社ウェブテクノロジがブース出展&セッションへの登壇を行うことになりました!
こんにちは。ウェブテクノロジ開発部の山崎です。
まずは下の画像をご覧ください。
「Before」と「After」の写真が3秒ごとに切り替わり表示されていますか?


以下の写真は OPTPiX WebFree のフィルター機能「エンハンストフィルター」の紹介用に、漫画作成ソフト「コミPo!」 のイベントでナビゲーターを担当して頂いている越谷先生のモデルの方にプライベート写真をご提供いただきました。ありがとうございました。




さて、「Before」が提供いただいたオリジナルの写真です。「After」がOPTPiX WebFree のエンハンストフィルターを通した写真です。
明るさやクッキリ具合が変わっているところがご覧いただけると思います。
ソーシャルネットワークの利用が増え、さらにスマートフォンなどで気軽に写真が撮れる状況も相まって、ブログやTwitterなどに写真を投稿する人もどんどん増えているようです。
気軽に公開できるのはよいのですが、撮った写真をそのままでは、ちょっと被写体が小さかったり、
横になって写っていたり、関係の無いところが写っていたり、暗くてよくわからなかったり、・・・あとすこし変えられれば公開できるのに・・・と、あと一歩のところでためらってしまった経験はありませんか?
そんな時に使ってほしいサービスがこちら
無料画像加工サービス「OPTPiX WebFree」
写真の中から必要な所だけを切り抜いたり(トリミング)90度回転させたり、縦横サイズを拡大したり、縮小したり。
そして、どんな写真でもおまかせの変換の「エンハンストフィルター」がオススメです。
料理の写真などを美味しく変換しますし、顔の写真もクッキリとお見せします。
特に、はじめの画像のような料理の写真で威力を発揮します。
「せっかく撮ったのに、ちょっと暗いんだよね」と感じたら、エンハンストフィルターを使ってみてください。
クッキリと明るく!そして美味しそうに写真を加工します。しかも無料でご利用いただけます。
ぜひ、お試しください。
本日の「OPTPiX Labs Blog」では、画像サイズの縮小方法についてお伝えしたいと思います。
最近、スマートフォンがかなり市場に出回りスマートフォンのアプリが増えてきました。スマートフォンアプリ開発において、最近よく耳にするのが、アプリデータのサイズ縮小です。
スマートフォンアプリのアプリデータサイズを20MB以内に縮小することが、最終的なアプリの売れ行きに一役買うようです。
先月開催されたCEDEC の講演「忍者ロワイヤルの今までと今後」の中で当社の画像最適化ツール「OPTPiX imesta シリーズ」が特に画像サイズ縮小機能にフォーカスして紹介されました。
特にスマートフォン表示向けに画像サイズを縮小する際に有効というご紹介をいただきましたのでここではその内容をご紹介いたします。
こちらの講演での紹介内容のポイントは、画像サイズの軽量化です。
特にiPhone 向けのアプリケーションでは、アプリのサイズを「20MB以内」に抑えることが重要とされており、そのために、画像のインデックスカラー化、つまり「減色」を利用したとのことです。
忍者ロワイヤルでは、当社のOPTPiX imesta を利用していただくことで高品質な画像のままアプリケーションのサイズを「20MB 以内」に抑えることができたそうです。
特に「透過情報までインデックスカラーとして扱えるところ」が「ユニーク」だと紹介されました。
多くの画像サイズ縮小ソフトの中で、当社のOPTPiX imesta をご利用いただき画像品質を落とすことなく、画像サイズの縮小に効果を発揮したとのこと大変うれしく思います。
スマートフォン向けウェブサイトで採用した場合でも、画像サイズが縮小されるため表示の高速化、全体的な品質の向上が見込めます。
ぜひ無料トライアルサービスをご利用下さい。
OPTPiX imesta for Mobile &Socialの無料トライアルはこちら
なお、ご紹介したCEDECの講演「忍者ロワイヤルの今までと今後」の記事へのリンクはこちらです。
では、続いて”画像サイズの縮小”をテーマに次の事例を紹介します。
i-Mode黎明期から携帯コンテンツを手がけるA社様では携帯SNSコンテンツのアバターキャラクター、およびコンテンツ自体のフィーチャーフォン向け最適化に、長らくOPTPiX imesta 7 for Mobile & Socialをご利用いただいています。
ベースになるアバターキャラクターをある程度のまとまった単位で共通パレットを作成して減色。
加えて、アバターを彩るアイテムデータも同じく”OPTPiX imesta 7″の「共通パレット減色」を
使うことで、画像データのサイズを縮小化。
結果、コンテンツ全体のサイズと、データ転送量の節約に効果を発揮したとのこと。
また、同サービスのスマートフォン対応では、スマートフォンの高解像度化に合わせて大元となった画像データを再度リサイズ。
フルカラーが使える端末とは言えキャリアによっては3G回線がフルレートでないこともしばしば。
そこで、”OPTPiX imesta 7″の「アルファチャンネル対応減色」機能を使い、フルカラーと見分けがつかないクォリティの画像を用意し、無事にサービスを開始することができました。
3週間おきのアイテムリリースも、デザイナーの手を煩わせることなく誰でもマウスをクリックするだけで実行できるようプロジェクトのスリム化に成功。
およそ1人月のコストダウンにも貢献したとのことです。
なお、OPTPiX imesta for Mobile & Scoial は以下のページをご覧ください。
OPTPiX imesta for Mobile & Socialの詳細はこちら
OPTPiX imesta シリーズには姉妹製品もあります。当社の製品一覧は以下のページをご覧ください。
ウェブテクノロジ代表の小高です。
今回は、ほぼ趣味の話ですが、ご興味ある方はお付き合いください。
先日、秋葉原の電子部品店である若松通商さんが企画した「mbed版パーソナルモニタリングポストMark2ハンズオンセミナー」というセミナーに参加して、いわゆるガイガーカウンタ(放射線量の測定器)のキットを自作(組立)してきました。
この製品(以下、Mark2)の存在を知ったのは、コミPo! ブログの記事です。キットのマニュアルがコミPo! を使って描かれているということで、コミPo! ブログで紹介されています。
Mark2について簡単に説明しますと、基本はGeiger-Muller計数管(GM管)を使ったガイガーカウンタなのですが、Ethernet I/Fがついていて、測定結果をインターネットに送信できる機能を持っています。このため、製品名がガイガーカウンタではなく、パーソナルモニタリングポストになっているのだと思います。
セミナーの参加条件が「はんだづけのできる方限定」にもかかわらず、受け付け開始からまもなく定員いっぱいになったようで、人気ぶりが伺えます。
セミナーにはMark2を開発された木幡(こわた)さんも参加されるということで興味を持ち、参加を決めました。ちなみに、趣味なのでポケットマネーです。

組立中の様子。フラックスの溶ける匂いが漂う
当日の様子は、若松通商 アキバNET館とCQ出版社エレキジャックのページでも詳しく紹介されています。
参加者の平均年齢は結構高め、でしたが、近くのメイド喫茶橙幻郷から参加したメイドさん2名が平均値の引き下げに大きく貢献していました。なんと、彼女たちも参加条件をクリアしていて、頑張ってはんだづけしていました。

メイド喫茶橙幻郷から派遣されたしおんさんとかなえさんも、自分たちではんだづけしていました
ところで、私自身、20年前にソフトウェア会社を設立しましたが、小学6年生のときに電子工作に目覚め(?)、秋葉原に通って半導体部品を買い、独学ではんだづけを覚えて、中学高校生の頃はせっせと電子工作をしていたいわゆるラジオ少年(世代的には、もうラジオを作る時代ではなかったので、IC少年?)でした。
デジタル回路だけでなく、アナログ回路(楽器用のエフェクターやミキサー、ヘッドフォンアンプ、実験用の電源回路など)も良く作っていました。若松通商さんで初めて買い物をしたのも、30年以上前になります。
大学生になってからは、秋葉原の某有名パーツ店でのアルバイトを経て、月刊プロセッサというハードウェア雑誌の編集部で掲載記事用の電子回路組立(部品調達からはんだづけ、動作確認まで)のアルバイトをやっていました。その後、月刊プロセッサで連載を持たせていただいて、PC-9800用拡張ボードの製作記事を執筆したこともあります。
という経歴があるため、この20年以上、滅多にはんだづけをしなくはなりましたが、Mark2の組立は早々に終了。一発完動でした。
もちろん、もともとのキットの設計が良いことも、大きな理由だと思います。それは、セミナーの参加者全員が、完動したことからも伺えます。調整箇所もなく、再現性の高いキットだという印象です。

完成したMark2。手前のアルミ管に入っているのがGeiger-Muller計数管。青色LEDの付いたドーターボードがmbed
下の写真は、完成後に校正用の放射線源を使って、堀場製作所製のガイガーカウンタと比べて簡易校正しているところです。この日に組み立てた複数の装置で、どれも近い値が出ています。
Mark2で使われているGM管は、ロシア製のSBM-20というものですが、(素人の感覚ですが)意外と製造上のバラツキが少ない印象を受けました。
放射線遮蔽をした環境で校正したわけではないので、高精度ではありませんが、大まかな目安を知るには充分だと思っています。

校正中の様子。組み立てたキットと、持ち寄られた各種ガイガーカウンタ。中央の黄色い円盤が線源

Cs-137(セシウム137)の校正用線源。原子核崩壊していくので、製造年月と半減期が記載されている
手堅いキットの組立とは言え、回路図を見て動作原理を理解しながら物作りをする楽しさを久々に思い出しました。最初に電源を投入するときが、やっぱり一番緊張します。大きなミスがあると、高価な部品を壊してしまう場合もありますから。
Mark2では、マイコン部分にmbedというモジュールを利用しています。mbedは、ARMコアを使った1チップマイコンと周辺回路をDIP型の基板に実装して、自作装置を作りやすくしたモジュールで、USBやEthernet I/Fも備えています。なにより一番面白い特徴は、ブラウザ上でIDE(統合開発環境)が動くことでしょうか。
私が趣味で電子工作をしていた時代、TTL 7400シリーズやC-MOS 4000シリーズを使った回路図を手で書いていたのとは隔世の感です。Ethernet搭載機器がこんなに簡単に作れるとは。
今回のセミナーを企画された若松通商 アキバネット館 館長の小暮さんは、エレクトロニクス産業の基礎を支える秋葉原の再興を目指して、日々活動をされているとのことです。小倉さんは私と同世代で、少年時代から秋葉原通いをしていたという共通点もあり、非常に共感を覚えました。
いま、日本のエレクトロニクス産業は岐路に立たされていますが、秋葉原のように、エレクトロニクス産業とコンテンツ産業が融合することで、今後も世界のなかで重要なプレゼンスを確保していって欲しいと願っています。
Mark2設計者の木幡さんは、もともとのお住まいが福島第一原子力発電所の避難区域にあり、避難生活をしながらMark2の設計をされたそうです。
最後になりましたが、木幡さんをはじめ、被災者の皆様の生活が少しでも早く好転することをお祈りしております。