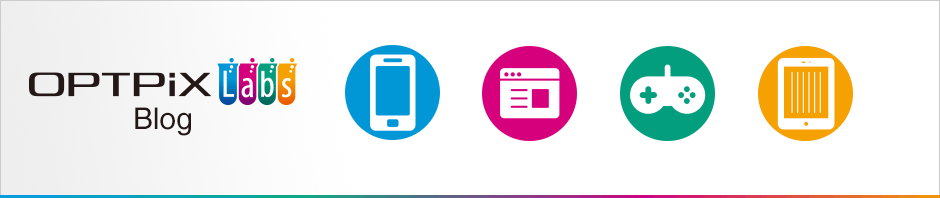「政府は景気が回復しているというけれど、少しも実感することができない。」
これは、小泉政権のころからず〜っと世間で言われ続けていることだ。こんな話を聞くたびに私は周囲の人に「じゃあどうなったら景気が回復したと実感する?」と聞いている。様々な答えが返ってくるけれど、総合してみると「バブルの時代が戻ってくれば」というのが一般的なようだ。なるほど、好景気とはまさにあの時代を指して言うのだろう。
しかし冷静に考えてみてほしい、「バブル」と名前がついてることから、この好景気は「弾けることが前提」であり、決して人々を幸福にするものではないのだ。
ボクはよく20代の人から「あなた方はいいですよね。バブルの時代にいい思いをしたのでしょう。」と言われることがある。
しかし、あの時代ボクは社会人になったばかりで、いい思いなんかほとんどしちゃいないのだ。バブル期にいい思いをしたのは、経営者から課長ぐらいまでの管理職ではないだろうか?ペーペーの新人は、毎晩遅くまで残業し頻繁に休日出勤し、給与もボーナスも決して高いものではなかった。あの時代は、まだ完全週休2日でない会社も多く残っていたし、ブラック企業も横行していた。
あの当時、玩具問屋に勤めていた知人の体験談を紹介しよう。
知人は、商品を卸している百貨店の玩具売り場で、毎週土日に売り子をしていた。アルバイトではなく、問屋の百貨店へのサービスの一環として無償で販売応援をやらされていたのだ。百貨店側が要求したのかもしれない。ま、当時は玩具売り場に限らず百貨店や量販店の多くの売り場が、卸問屋の無償の協力により人件費を節約してた。その知人は、月曜から金曜日は通常の問屋業務、土日は百貨店で販売応援。つまり365日休みなしの完全労働であった。会社の規則では代休が取れるはずであったが、日常業務が忙しく取ることは不可能だったという。
このような無茶苦茶な労働環境は、バブル期には珍しいものでもなく、特に20代の社員は、馬車馬のように働かされていた。貴族のように毎夜のごとく宴を楽しんでいたバブル期のサラリーマンたちを影で支えていたのが、奴隷のような若手サラリーマンたちだったのである。
さて、知人の話に戻るが、そのような過酷な状況にあったもののボーナスは年に2回ちゃんと出た。そこはそこ、好景気ならではである。
しかし、彼にはさらなる試練が待ち受けていた。勤めている玩具問屋では、ボーナスの支給日にはなぜか社長の奥さんが来社する。社員の労をねぎらうのかというと、そうではない。奥さんは中規模のふとんメーカーを経営している。ボーナスをもらって上機嫌な若手社員をつかまえては「あなた顔色が悪いわよ。大丈夫?きっと寝具が合ってないからよ。」といい、高級なふとんを薦めてくれるのだ。なんと親切な奥さんでありましょうか。
かくして、365日働かされて、やっとボーナスを手にした私の知人は、奥さんに逆らうことができず、高額な布団を買わされてしまったのである。彼だけではない、その玩具問屋の若い社員はほとんど、その高級寝具を買うことになるのである。こうして、社員たちに支払われたボーナスは、社長一族の所に戻っていくのであった。これはギャグでもコントでもなく、その時代にあった実話である。
そんなわけで、20代のみなさん、華やかな好景気は奴隷階級が支えていたという事実を知ってください。そして、あの時代にはブラック企業をネットで告発するという仕組みもなく、深夜残業の後でおつきあいの飲み会と、その場での上司のパワハラに笑顔で耐えなきゃいけないボクたちがいたということを知ってください。あのような好景気は、二度と繰り返してはいけない悲劇なのです。